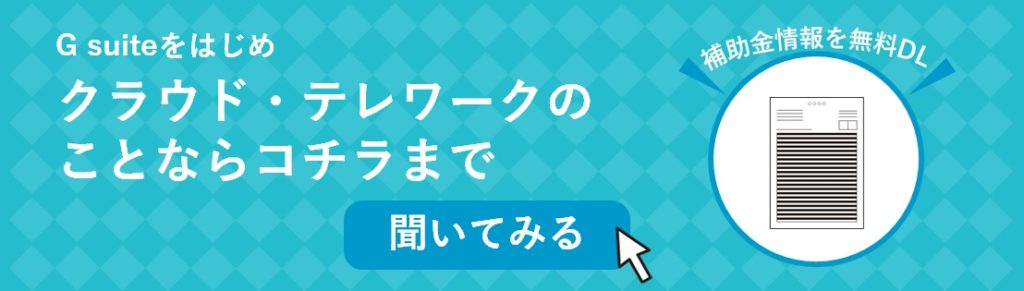仕事を行う上で必要不可欠な情報共有。近年、この情報共有を適切に行うことで業務効率化を促進しようとする試みが、多くの企業で行われています。
そこで今回は、情報共有の重要性やメリット・デメリット、役立つツールをご紹介していきます。
今回の記事を参考に、ぜひ情報共有ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
- 1 情報共有の必要性
- 2 情報共有ツールのメリット
- 3 情報共有ツールのデメリット
- 4 情報共有ツール導入時の注意点
- 5 おすすめ情報共有ツール14選
- 5.1 【情報共有ツール①】slack
- 5.2 【情報共有ツール②】chatwork
- 5.3 【情報共有ツール③】Incircle
- 5.4 【情報共有ツール④】wowtalk
- 5.5 【情報共有ツール⑤】LINE WORKS
- 5.6 【情報共有ツール⑥】Talknote
- 5.7 【情報共有ツール⑦】Chat&Messenger
- 5.8 【情報共有ツール⑧】Microsoft Teams
- 5.9 【情報共有ツール⑨】Stock
- 5.10 【情報共有ツール⑩】Evernote
- 5.11 【情報共有ツール⑪】kibela
- 5.12 【情報共有ツール⑫】Dropbox
- 5.13 【情報共有ツール⑬】Google Drive
- 5.14 【情報共有ツール⑭】box
- 6 まとめ
情報共有の必要性
業務を円滑に進めるには、効率的で正確な情報共有が必要不可欠です。
一緒に仕事を行うメンバーはもちろん、上司やクライアントなど、とても多くの場面で必要な情報共有が上手くいかない場合、伝達不足や認識の相違から、様々なミスが発生してしまいます。
そんな情報共有を円滑に進めるためには、社内の雰囲気やメンバー同士の信頼などに加え、ツールを使うことも重要です。
情報共有ツールのメリット
【情報共有ツールのメリット①】コミュニケーションの増加
情報共有ツールには、チャット機能や社内SNSなどの社内のコミュニケーションを活発化させる様々な機能が揃っています。
情報共有の質を高めるためには、ツールに頼るだけでなく社内の雰囲気など、アナログな部分も改善する必要があります。情報共有ツールは、そのような部分の足掛かりとしても役立ってくれるでしょう。
【情報共有ツールのメリット②】業務効率化
情報共有ツールを用いることの大きなメリットの1つとして、各個人が持つノウハウを集約することができる点が挙げられます。
これによって、スキルや知識を社内で共有することができ、業務効率化に繋げることができます。
【情報共有ツールのメリット③】情報へのアクセスが容易に
情報共有ツールとしての機能の1つとして存在するクラウドストレージ。これを用いて社内のデータを一か所に集約することで、情報へのアクセスをより簡単に行うことができるようになります。
さらに、web上に保存するため、どこからでもデータにアクセスすることも可能。テレワークの促進にも役立ちます。
情報共有ツールのデメリット
【情報共有ツールのデメリット①】不必要なコミュニケーションの増加
コミュニケーションの活発化をメリットとして挙げましたが、使い方を一歩間違えると不要なコミュニケーションが生まれてしまい、ツール導入前より業務効率性が悪化してしまう可能性があります。
情報共有ツールを導入する際は、使い方をしっかりと定めてから利用するようにしましょう。
【情報共有ツールのデメリット②】情報の量の過剰増加
さらに、情報共有ツールを用いることで情報の量が増加しすぎてしまい、必要な情報にたどり着けなくなってしまう可能性があります。
社員それぞれが、共有するべき情報かどうかをしっかりと判断して利用できるように、ツール導入前に準備を行うことをおすすめします。
情報共有ツール導入時の注意点
【ツール導入時の注意点①】現状の課題を解決できるか考慮する
情報共有ツールの中でも、様々な種類のものが存在し、何を解決したいかで利用するべきツールも変わってきます。
現状の課題をしっかりと洗い出し、どのようなツールをどのように使うかをしっかりと考慮するようにしましょう。
【ツール導入時の注意点②】セキュリティの安全性に注意する
上でも述べたように、数多くの情報共有ツールが存在しています。
そこで機能の他にセキュリティの安全性も考える必要があります。特に、クラウドストレージなどweb上にデータを保存する場合は、情報の漏えいなどを防ぐ為にもしっかりと考慮するようにしましょう。
おすすめ情報共有ツール14選
【情報共有ツール①】slack

Slackは、世界中の企業で導入されている情報共有ツールです。
その特徴として最初に挙げられるのが使いやすさです。シンプルながら、様々な外部ツールと連携可能な点や、チャットの投稿後に修正が可能な点など、ユーザー目線で考えられた使いやすい機能が揃えられています。
さらにエンターテイメント性に富んでいるのも他の情報共有ツールには見られない特徴。
オリジナルの絵文字を作成して使用できたり、チャットルームを細かくカスタマイズ性能できたり、自然とコミュニケーションが促進されるような工夫が施されています。
【情報共有ツール②】chatwork

Chatworkは、Chatwork㈱が提供している情報共有ツールです。
コミュニケーションのための様々な機能が揃っており、社内・外を問わず利用することができます。Gmailなどの外部ツールとも連携可能な点も嬉しいポイント。
さらに、フリープランでもユーザー数に制限なく利用できるのもメリットといえるでしょう。無料でもしっかりと活躍してくれる情報共有ツールの1つです。
【情報共有ツール③】Incircle

Incircleは、AI CROSS株式会社が提供している情報共有ツールです。
情報共有のための基本的な機能に加え、AIを利用した離職防止ソリューションや、充実した管理機能が備えられています。
その一方で、グループウェアのような業務効率化を促進する機能は備わっていないため、導入時に必要な機能をしっかりと検討するようにしましょう。
【情報共有ツール④】wowtalk

WowTalkは、ワウテック株式会社が提供している情報共有ツールです。
”「働き方改革」は「コミュニケーション改革」から!”というコンセプトを軸に作成しており、業務効率化やコスト削減を促進できる様々な機能が揃えられています。
さらに個人単位で機能のカスタマイズが可能。利用する方それぞれにあった使い方ができるのも他の情報共有ツールと比べ嬉しいポイントです。
【情報共有ツール⑤】LINE WORKS

LINE WORKSは、LINEが提供する情報共有ツールです。
使い勝手は普段使用しているLINEのままに、ビジネスの為に用意された様々な機能を利用することができます。
情報共有ツールをはじめて利用する方でも、すぐにその操作性に慣れることができるのも嬉しいポイントです。
【情報共有ツール⑥】Talknote

Talknoteは、Talknote株式会社が提供している情報共有ツールです。
チャット機能やタスク管理などの基本的な情報共有ツールとしての機能に加え、各社員のやり取りやコミュニケーションを分析する機能が備えられています。これによって、モチベーションやコミュニケーション量の可視化、離職意向検知、オーバーワーク検知などを行うことができます。
様々な機能が揃っており、コストパフォーマンスの高い情報共有ツールといえrのではないでしょうか。
【情報共有ツール⑦】Chat&Messenger

Chat&Messengerは、株式会社Chat&Messengerが提供している情報共有ツールです。
複数人で利用可能なビデオ通話機能に始め、通話中のデスクトップ画面の共有機能などユーザー目線で考えられた使いやすい機能が多く揃っています。
無料プランでもユーザー数の制限なく利用可能なのも嬉しいポイント。導入時には社内ユーザーを自動で識別してくれるため、面倒な設定も必要ありません。
「とりあえず使いやすい情報共有ツールを利用したい」という企業におすすめです。
【情報共有ツール⑧】Microsoft Teams
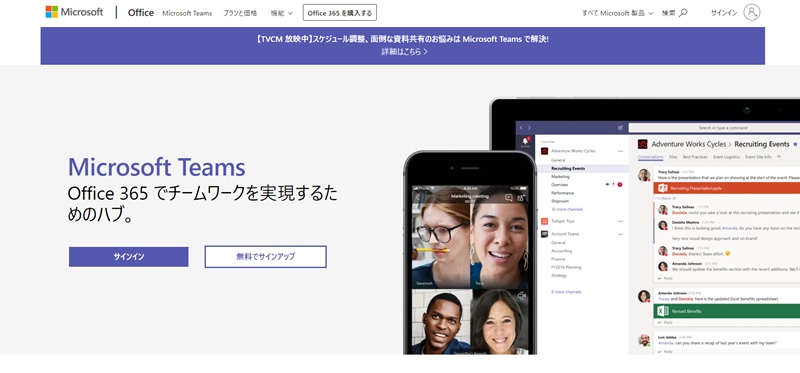
Microsoft Teamsは、Microsoftが提供している情報共有ツールです。
基本的な情報共有ツールとしての機能は一通り備えており、そのほかにもファイル管理機能などの多くの便利な機能を揃っています。
Office365へのアップグレードも可能なため、より多くの機能やストレージ容量が必要な場合にも簡単に対応することが可能です。
【情報共有ツール⑨】Stock

Stockは、株式会社リンクライブが提供している情報共有ツールです。
”驚くほど簡単に「チームの情報ストック」と「タスク管理」ができる”というコンセプト通り、チャットツールとしての機能を高めながら、情報管理の容易さ・正確さも追及されています。
「通常の情報共有ツールだと必要な時に欲しい情報が手に入らない」、「タスクの管理をもっと簡単にしたい」とお悩みの企業にうってつけのサービスです。
【情報共有ツール⑩】Evernote

Evernoteは、テキストなどのデータを保存できる情報共有ツールです。
メモ機能としての機能に特化しており、テキストデータの他にも、画像や音声、動画などもクラウド上に保存することができます。
【情報共有ツール⑪】kibela


kibelaは、社内の情報を集約することで、情報の共有・伝達を円滑にするサービスです。
kibelaには「wiki」と呼ばれるチーム全体で情報を共有する方法と、個人で情報を共有する「blog」の2種類の情報有方法が存在します。この2つを適切に使い分けることで、効率的に情報を共有することができます。
【情報共有ツール⑫】Dropbox
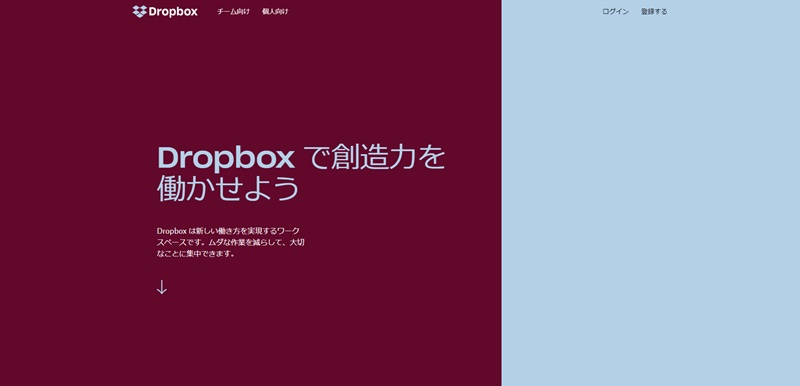
Dropboxは、web上にデータを保存・ダウンロードなどができる情報共有ツールです。
無料プランでは、利用開始時は2GBまで利用することができ、友達を招待することで最大16GBまで容量を増やすことができます。
【情報共有ツール⑬】Google Drive

Google Driveは、Googleが提供している情報共有ツールです。
こちらも上で紹介したDropbox同様、web上にデータを保存することができるクラウドストレージサービス。
様々な外部ツールと連携することができ、その中でも特にGoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントなど、Googleが提供するサービスとの親和性は抜群です。
無料プランでも15GBまで利用することができるため、「情報共有ツールにお金をかけたくない」という方にもおすすめです。
【情報共有ツール⑭】box
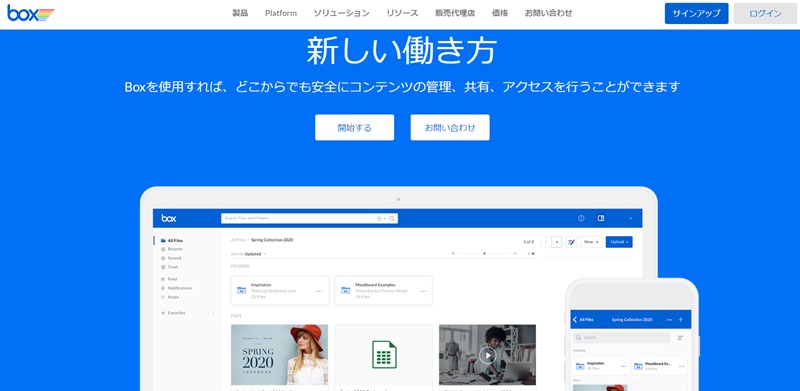
boxは、主に企業向けに開発された情報共有ツールです。
こちらも上記2つのツール同様にクラウドストレージとしての機能が充実しています。数ある情報共有ツールの中でも、多くの企業に人気の理由として、そのセキュリティの高さが挙げられます。
その他にも、権限管理の柔軟さも人気の理由として挙げられます。編集や閲覧はもちろん、リンクの取得やアップロード、ダウンロードにも権限による制限をかけることができます。
まとめ
今回は情報共有ツールについて、メリット・デメリットやおすすめのものをご紹介しました。
情報共有ツールを使用することで、以前よりも容易にコミュニケーションの質を高められる昨今。適切なツールを選び、使いこなす能力が求められています。
意識をしていない状況では、課題が見えてこないのも情報共有の特徴。ぜひ今回の記事を参考に、今一度社内の状況を振り返ってみてはいかがでしょうか。
また、QQLNEでは今回ご紹介したような業務効率化ツールに関するプランニングや、G Suiteの導入支援を行っています。
ご利用を検討されている方は、ぜひ下記ページからご連絡ください。